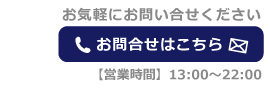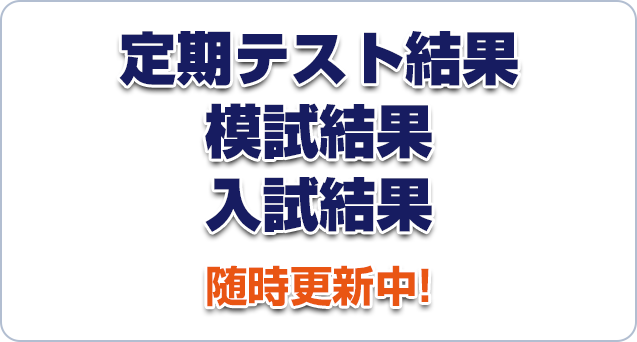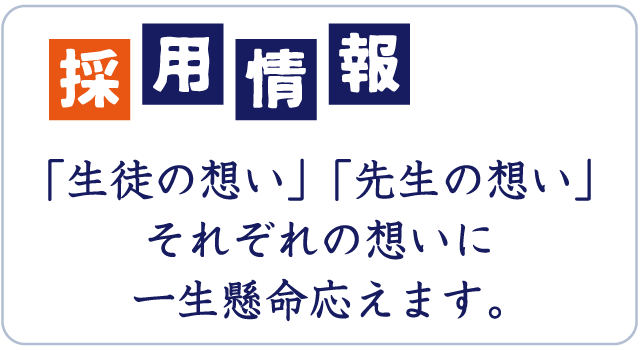こんにちは!Yes進学セミナーです!今回は、「国語の読解力をつける方法」についてお伝えしたいと思います!
「国語は得意??」と生徒に聞くと、大抵こんな答えが返ってきます。
「どう勉強すればいいか分からない」
「勉強してもしなくても点数変わらない」
「問題によって良かったり悪かったりする」
生徒の気持ちはわかります。私も学生の頃は同じようなことを考えていました。
たしかに、国語は他教科とは少し異なった性質を持っているのかもしれません。
しかし、国語が受験科目の1つに位置付けられていることからも分かるように、
他の科目と同様、適切に勉強をすることで成績が上がるものであることは明白です。
ここで、国語とはどのような教科であるのか、私の考えを述べさせていただきます。
1.「本文」という未知の課題文をその場で理解し、
2.「解答」という形でその理解を表現する試験 である。
1.について、ここが他教科と国語の大きな違いであると考えられます。
試験までに教科書から問題の解き方を記憶、理解する他教科とは異なり、
国語はこれまでに見たことも読んだこともないような「本文」をその場で読解しなければなりません。
「本文」を限られた試験時間でいかに理解できるか、まずこれが1つ目のポイントとなります。
2.について、ここは他教科にも通ずる部分ですが、問いに対して適切に解答する必要があります。
ここにはテクニックやコツも存在しますが、やはり1.ができていなければ、それらのほとんどが意味のないものになるでしょう。
つまり、国語においては読解が重要事項です。
同じ本文が出題されることはないため、力をつけるためには本文を読解する訓練を行わなければなりません。
ではここから、国語の読解力を身につける3つのポイントをご紹介します!
↓
↓
①語彙を増やす
文章は1文の積み重ねであり、1文は単語から成っています。
最小単位である単語の意味が分からなければ(語彙力が無ければ)、文字の大海を彷徨うことになるでしょう。
とはいえ、辞書を丸暗記する必要はありません。
大切なのは、自分なりに言い換える力と推測する力です。(前のブログの漢字の勉強も語彙をつけるのに役立ちます)
普段から知らない言葉があれば、まず推測し、調べることを習慣づけましょう。
②本文を構造的に捉える
国語の問題に出される文章には必ず、回答者に理解してほしい構造があります。
小説では、登場人物の心情の変化
説明文では、言い換えや対比、因果関係などです。
国語の文章は、この関係が段落ごとにあり、そして全体の構造を作っていきます。
文章を構造として捉えることが、読解の力であるといえます。
③解き方を学ぶ
最後は、①②を使って理解した内容を表現する方法です。
国語の問題(特に選択肢問題)は回答者を間違わせようとしています。
ここには特徴があり、
例えば、本文にはそもそも書いていないパターンや、
最もらしいことが書かれていても、傍線部分とはなんら関係のないパターンなどがあります。
問題を漫然と解くのではなく、これらのパターンを意識することで、ミスが減るでしょう。
以上が読解力をつける3つのポイントです!
これらのポイントを押さえながら1人で勉強するのは大変なことです。
Yes進学セミナーでは、講師がこれらのポイントを生徒に分かりやすく伝えております!
国語が苦手…という方は、Yes進学セミナーで国語を得意に変えましょう!!!